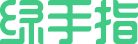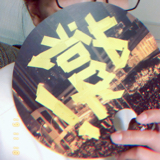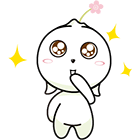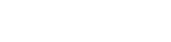文章
玲儿
2017年08月10日

トウガラシ(観賞用)の育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
鉢植えは、日当たりと風通しのよい場所に置きましょう。庭植えにする場合は、肥沃で日当たりと水はけのよい場所に植えつけましょう。水はけが悪い場所では、土を高く盛ったり、腐葉土を入れて水はけをよくし、やせた土地では、堆肥を施してから植えつけましょう。
水やり
鉢植えでは、鉢土の表面が乾いてきたら、たっぷり水を与えましょう。庭植えでは、梅雨明けから8月下旬までは、4~5日に1回、たっぷり水を与え、過度に乾かしすぎないほうが、株が大きく育ちます。

肥料
鉢植え、庭植えともに、5月から9月の間、緩効性化成肥料(チッ素N-リン酸P-カリK=10-10-10)を施します。
病気と害虫
病気:特にありません。
害虫:アブラムシ、ハダニ
4月から11月、特に新芽にアブラムシが発生しやすいのでよく観察し、発生したら防除しましょう。
4月から10月の成長期を通して、ハダニが発生します。特に高温と乾燥が続く夏に発生が多くなります。水やりのたびに葉裏にも水がかかるようにすると、発生が抑えられます。

用土(鉢植え)
水はけがよく肥えた土を好みます。赤玉土(中粒)5、腐葉土2、完熟堆肥1、酸度調整済みピートモス2の配合土などを用い、元肥としてリン酸分の多い緩効性化成肥料を適量混ぜて植えつけましょう。

植えつけ、 植え替え
植えつけ適期は5月から8月です。根鉢をくずして植えつけると新芽がよく伸び、大きく育てることができます。寄せ植えや小さな鉢を用い、あまり株を大きくしたくないときは、すでに実がついた株を根鉢をくずさずに植えつけると、新芽の発生が遅くなり、小さな株の状態が長く保てます。植え替えの適期は7月から8月です。根が伸びる勢いが強く根詰まりしやすいので、夏に鉢増しするとよく育ちます。

ふやし方
タネまき:5月から6月が適期です。トウガラシは発芽に25~30℃の高温が必要なので、早まきは避けましょう。早まきすると発芽しなかったり、発芽しても葉の形が歪んだりすることがあります。
主な作業
特にありません。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
鉢植えは、日当たりと風通しのよい場所に置きましょう。庭植えにする場合は、肥沃で日当たりと水はけのよい場所に植えつけましょう。水はけが悪い場所では、土を高く盛ったり、腐葉土を入れて水はけをよくし、やせた土地では、堆肥を施してから植えつけましょう。
水やり
鉢植えでは、鉢土の表面が乾いてきたら、たっぷり水を与えましょう。庭植えでは、梅雨明けから8月下旬までは、4~5日に1回、たっぷり水を与え、過度に乾かしすぎないほうが、株が大きく育ちます。

肥料
鉢植え、庭植えともに、5月から9月の間、緩効性化成肥料(チッ素N-リン酸P-カリK=10-10-10)を施します。
病気と害虫
病気:特にありません。
害虫:アブラムシ、ハダニ
4月から11月、特に新芽にアブラムシが発生しやすいのでよく観察し、発生したら防除しましょう。
4月から10月の成長期を通して、ハダニが発生します。特に高温と乾燥が続く夏に発生が多くなります。水やりのたびに葉裏にも水がかかるようにすると、発生が抑えられます。

用土(鉢植え)
水はけがよく肥えた土を好みます。赤玉土(中粒)5、腐葉土2、完熟堆肥1、酸度調整済みピートモス2の配合土などを用い、元肥としてリン酸分の多い緩効性化成肥料を適量混ぜて植えつけましょう。

植えつけ、 植え替え
植えつけ適期は5月から8月です。根鉢をくずして植えつけると新芽がよく伸び、大きく育てることができます。寄せ植えや小さな鉢を用い、あまり株を大きくしたくないときは、すでに実がついた株を根鉢をくずさずに植えつけると、新芽の発生が遅くなり、小さな株の状態が長く保てます。植え替えの適期は7月から8月です。根が伸びる勢いが強く根詰まりしやすいので、夏に鉢増しするとよく育ちます。

ふやし方
タネまき:5月から6月が適期です。トウガラシは発芽に25~30℃の高温が必要なので、早まきは避けましょう。早まきすると発芽しなかったり、発芽しても葉の形が歪んだりすることがあります。
主な作業
特にありません。
0
0
文章
玲儿
2017年08月10日

チャイブの育て方・栽培方法
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
弱アルカリ性で水もちと水はけのよい肥沃な土を好みます。日当たりがよすぎると、葉が堅くなることがあります。高温乾燥には弱いので、夏は半日陰で管理します。冬は葉がなくなりますが地下茎は生育しており、春に芽を伸ばします。
水やり
乾燥には弱く、特に成長期に水が不足しないように水やりをします。
庭植えは、晴天が続く4月から5月ごろに水が不足すると、葉の先が枯れてきます。葉がよく伸びる時期には、水やりをします。
鉢植えは、冬は地上部がなくなりますが、乾燥しすぎないよう忘れずに水をやります。

肥料
庭植えは、植えつけの数週間前に腐葉土、堆肥、有機質肥料(または緩効性肥料)を、また1週間前に苦土石灰をすき込んでおきます。
鉢植えは、用土に元肥として緩効性肥料を加えます。
肥料が不足すると葉先が黄色くなってきます。成長期には、水やりを兼ねて液体肥料を施すか、緩効性肥料を株元から離れたところに置きます。
病気と害虫
病気:ネギさび病
降雨が多い春と秋に、ネギさび病が発生することがあります。
害虫:アブラムシ
春と秋にアブラムシが発生することがあります。
用土(鉢植え)
弱アルカリ性で水もちと水はけのよい肥沃な土を用います(例えば、市販の野菜用培養土、または赤玉土小粒と腐葉土を1:1の割合でブレンドしたものに、それぞれ少量の苦土石灰を混ぜる)。

植えつけ、 植え替え
植えつけ:発芽した苗が10cmくらいに育ったら、数本をまとめて1株にして定植します。深さ2~3cmに植えつけます。
植え替え:年数がたつと、葉が堅くなったり、ふえて葉が細くなったりするので、株分けを兼ねて植え替えます。こぼれダネから芽生えた苗は、春か秋に育てたい場所に植え替えます。
ふやし方
タネまき:開花後、黒く完熟したタネがこぼれてふえますが、採種して秋にまくこともできます。発芽時に光を嫌う嫌光性種子なので、タネまき後は土を厚めに1cmほどかぶせます。春先は暖かくなってからのほうが発芽率は高くなるので、タネをまいた鉢などは日陰に置くのではなく、覆土して暖かい日当たりに置きます。タネから育てたものは、翌年にならないと花は咲きません。多年草ですが、年とともに葉が堅くなってくるので、3~4年を目安にタネまきや株分けで株を更新します。
株分け:地下茎が密集すると生育が悪くなるので、春か秋に株分けします。

主な作業
収穫:葉は地際から4~5cmのところで切って、適宜収穫します。収穫後は液体肥料を施しておきます。成長が早く、繰り返し収穫が可能ですが、収穫し続けると花は咲かないので、葉を収穫する株と、花やタネを収穫する株を分けます。たくさん収穫できたときは、細かく刻んで密閉容器に入れ、冷凍保存します。家庭での乾燥保存は向きません。

花が開いてきたらタネにならないうちに摘み、食用にします。花茎を根元から切って乾燥させ、ドライフラワーにすることもできます。花の収穫後は、葉を地面から5cmくらいまで切り戻して、新しい葉の成長を促します。
夏越しの工夫:株元をわらなどでマルチングすると、太陽熱による地温の上昇や余分な水分の蒸散を防ぐことができます。
育て方のポイント
栽培環境・日当たり・置き場
弱アルカリ性で水もちと水はけのよい肥沃な土を好みます。日当たりがよすぎると、葉が堅くなることがあります。高温乾燥には弱いので、夏は半日陰で管理します。冬は葉がなくなりますが地下茎は生育しており、春に芽を伸ばします。
水やり
乾燥には弱く、特に成長期に水が不足しないように水やりをします。
庭植えは、晴天が続く4月から5月ごろに水が不足すると、葉の先が枯れてきます。葉がよく伸びる時期には、水やりをします。
鉢植えは、冬は地上部がなくなりますが、乾燥しすぎないよう忘れずに水をやります。

肥料
庭植えは、植えつけの数週間前に腐葉土、堆肥、有機質肥料(または緩効性肥料)を、また1週間前に苦土石灰をすき込んでおきます。
鉢植えは、用土に元肥として緩効性肥料を加えます。
肥料が不足すると葉先が黄色くなってきます。成長期には、水やりを兼ねて液体肥料を施すか、緩効性肥料を株元から離れたところに置きます。
病気と害虫
病気:ネギさび病
降雨が多い春と秋に、ネギさび病が発生することがあります。
害虫:アブラムシ
春と秋にアブラムシが発生することがあります。
用土(鉢植え)
弱アルカリ性で水もちと水はけのよい肥沃な土を用います(例えば、市販の野菜用培養土、または赤玉土小粒と腐葉土を1:1の割合でブレンドしたものに、それぞれ少量の苦土石灰を混ぜる)。

植えつけ、 植え替え
植えつけ:発芽した苗が10cmくらいに育ったら、数本をまとめて1株にして定植します。深さ2~3cmに植えつけます。
植え替え:年数がたつと、葉が堅くなったり、ふえて葉が細くなったりするので、株分けを兼ねて植え替えます。こぼれダネから芽生えた苗は、春か秋に育てたい場所に植え替えます。
ふやし方
タネまき:開花後、黒く完熟したタネがこぼれてふえますが、採種して秋にまくこともできます。発芽時に光を嫌う嫌光性種子なので、タネまき後は土を厚めに1cmほどかぶせます。春先は暖かくなってからのほうが発芽率は高くなるので、タネをまいた鉢などは日陰に置くのではなく、覆土して暖かい日当たりに置きます。タネから育てたものは、翌年にならないと花は咲きません。多年草ですが、年とともに葉が堅くなってくるので、3~4年を目安にタネまきや株分けで株を更新します。
株分け:地下茎が密集すると生育が悪くなるので、春か秋に株分けします。

主な作業
収穫:葉は地際から4~5cmのところで切って、適宜収穫します。収穫後は液体肥料を施しておきます。成長が早く、繰り返し収穫が可能ですが、収穫し続けると花は咲かないので、葉を収穫する株と、花やタネを収穫する株を分けます。たくさん収穫できたときは、細かく刻んで密閉容器に入れ、冷凍保存します。家庭での乾燥保存は向きません。

花が開いてきたらタネにならないうちに摘み、食用にします。花茎を根元から切って乾燥させ、ドライフラワーにすることもできます。花の収穫後は、葉を地面から5cmくらいまで切り戻して、新しい葉の成長を促します。
夏越しの工夫:株元をわらなどでマルチングすると、太陽熱による地温の上昇や余分な水分の蒸散を防ぐことができます。
0
0